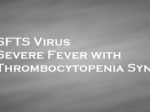病原性大腸菌
腸管出血性大腸菌(O157・O-157)
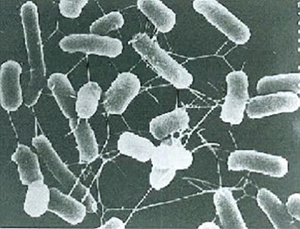
病原体について
大腸菌は人や動物の腸管に存在し、通常病原性はありません。
しかし、いくつかの大腸菌は人に対して病原性があり、これらは総称して病原性大腸菌(又は下痢原性大腸菌)と呼ばれています。現在、この菌は次の5つのタイプに分類されています。
特徴
大腸菌は人や動物の腸管に存在し、通常病原性はありません。しかし、いくつかの大腸菌は人に対して病原性があり、これらを総称して下痢原性大腸菌(病原大腸菌とも呼ばれています)と呼んでいます。現在、この菌は5つのタイプに分類されています。
1996年(平成8年)に全国で大きな社会問題となった腸管出血性大腸菌O157も下痢原性大腸菌のグループに入ります。VT1、VT2の2種類(あるいはいずれか1種類)のベロ毒素を産生する大腸菌で、出血性の大腸炎を起こします。感染しても健康な成人では無症状の場合や、単なる下痢であることがほとんどです。
しかし、乳幼児や小児、基礎疾患を有する高齢者では腹痛や血便などの出血性腸炎のほか、まれに急性腎不全、血小板の減少、貧血などの症状を呈する溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。
腸管出血性大腸菌O157は、牛、などの家畜が保菌している場合があり、これらの糞便に汚染された食肉からの二次汚染により、あらゆる食品が原因となる可能性があります。
便や食肉によるニ次汚染によりあらゆる食品が原因となる可能性がありますが、特に集団発生例では、給食や飲用水によるものが多く見られます。また、ベロ毒素産生性大腸菌では、米国でハンバーガーパティやローストビーフなど牛肉が汚染源となった事例が多く報告されています。大部分の事件で原因食品が特定されていないことから、予防対策が非常に立てにくくなっています。
病原体の種類ごとの潜伏期間と主な症状
1)腸管病原性大腸菌(EPEC)
12~72時間
下痢、腹痛を症状とし、サルモネラ属菌とよく似た急性胃腸炎を起こす。
2)腸管侵入性大腸菌(EIEC)
1~5日間
腸の細胞内へ入り、赤痢のような症状(血便、腹痛、発熱)を起こす。
3)毒素原性大腸菌(ETEC)
12~72時間
エンテロトキシンにより、コレラのような激しい水様性の下痢を起こす。
4)腸管出血性大腸菌(EHEC)
4~8日間
ベロ毒素により、腹痛や血便などの出血性腸炎を起こす。
ベロ毒素産生性大腸菌(VTEC)とも呼ばれている。
5)腸管集合性大腸菌(EAggEC)
1~5日間
腸の細胞に付着し、エンテロトキシンを産生することにより、散発的に下痢症を起こす。
腹痛、下痢、発熱(38℃~40℃)おう吐、頭痛などが主症状です。よって、潜伏期間は平均3~5日で、症状は激しい腹痛で始まり、数時間後に水様下痢を起こすことが多いです。
1~2日後に血性下痢(下血)がみられます。血性下痢は、ほとんどが血液で、糞便を含まないことがあります。また、溶血性尿毒症(HUS)や、脳障害を併発することがあります。HUSは、下痢が始まってから、約1週間後に、赤血球の破壊による、溶血性貧血、血小板の減少及び急性腎不全などの症状が現れます。重症の場合は死亡します。
注意すること
- 生野菜などはよく洗い、食肉は中心部まで十分加熱してから食べること。
- 冷蔵庫内の食品はよく点検し、早めに食べること。
- 加熱調理済の食品がニ次汚染を受けないよう、調理器具は十分に必ずよく洗う。できれば、熱湯又は塩素系消毒剤で消毒すること。
- 調理や食事の前には必ず石けんで手を洗うこと。
- 水道管直結以外の水を飲用あるいは調理に使用する場合は、必ず年1回以上の水質検査を受け、飲用に適しているか否かを確認すること。
- ビルなどの貯水槽の清掃・点検を定期的に行うこと。
- おなかが痛くて、下痢が続いたら、すぐにかかりつけの医師の診察を受けること。
- 発症した患者のいる家庭では、糞便に汚染された下着等の取扱いに注意すること。